身近には誰が決めたのか、いつからあるのかもわからない謎な基準やルールがあります。
疑問に感じた人は多いかもしれませんが誰に聞いても昔からあるから、昔からそうしてきたからといった曖昧な返答ばかりではないでしょうか。
この記事では、そういった謎の基準やルールの正体を紹介します。
謎基準の正体は「同調圧力」
身の回りにある誰が作ったのかわからない謎基準。
これらの正体は「人が空気を読むことで生まれる見えない力」であることが多く、これを「同調圧力」と呼びます。
特に協調性を重んじる日本社会には多くの謎基準が存在し、来日した海外の方を驚かせることもあります。
この項では、日本人が首を思いきり縦に振り、あるあると言ってもらえそうな謎基準(同調圧力)達を紹介します。
飲み会の「とりあえずビール」
「とりあえずビール」には多くの理由、心理が隠されています。
「周囲の人と合わせたくなる」「最初からビール以外のものを頼むと変に思われるかも」といった心理以外にも、「全員が同じ飲み物で乾杯することで一体感が強まる」といった心理が強く働くことで、とりあえずビールが使われています。
満員電車でリュックを前に抱える
多くの人が利用する電車には、小さなカバンから大きなキャリーケースを転がす人と、何らかの手荷物を抱えています。
中でもリュックは通常背負うことで使用するのに、電車内でいる人は前に抱えている光景をよく見かけます。
これは、後方の人に配慮したり、スリなどの被害に遭わないためにリュックは前に抱えることが理由です。
そして、この考えや行動を複数の人が実行することにより、同じ駅構内や車内でリュックを前に抱えている人が複数人いることでリュックを背負っている人は「とりあえず周囲に合わせておこう」と考えます。
スーツの色は「黒」か「紺」
就活などのシーンではスーツは「黒」か「紺」が常識とされおり、グレーなどの明るい色はダメではありませんが、周りから浮いた存在となることに恐怖心を持つ人が多くいます。
また、採用担当者の多くも黒か紺だと無難でいいのではないか、と答えることが多いようです。
ただ、企業の規則に明記されていない限り、明るい色のスーツでも問題はありません。
とりあえず周囲と同じにしておけば安心といった気持ちや、周りがそうしているからこれが正解だろうといった心理が働くことで黒か紺が絶対的な正解であるかのように見えてしまっています。
職場の空気が作る基準
勤めている職場にも「何となく帰れない空気」を感じてしまい、意味も無くエクセルやワードを開いたり閉じたり、何となくデスクを片付けたりして時間が過ぎるのを待つ経験をした人もいるかもしれません。
何となく帰れない空気(雰囲気)、これも同調圧力が働いています。
周りがまだ仕事しているのに先に帰って嫌われたくないや、他の人も残業しているからこれで正しいんだといった2つの要素が組み合わさることで、帰れない空気が出来上がっています。
会議での発言タイミング
職場の会議に参加した経験がある人は「自分が発言してもいいのか?」「上司や先輩が発言せずに静かにしているなら、それに従わざる得ない」といった状況に遭ったことがあるかもしれません。
これらにも強い同調圧力がかかっていると考えられます。
自分だけが発言したら周囲から浮くかもしれないや、自分の意見は間違っているかもしれないといった心理が働くことで発言するタイミングを失い、そのまま会議が終わってしまうことにつながります。
人はなぜ「同調圧力」に屈してしまうのか
人が周囲の空気を読むことで、その場では異質と捉えられかねない行動や発言をしないようにし、周囲と同じ行動をすることを「同調圧力」といいます。
人が同調圧力に屈してしまうのには様々な理由、心理が隠されています。
規範的影響
集団から孤立してしまうことで大きなストレスを抱えてしまうこと、「嫌われたくない」「変に目立ちたくない」など強い気持ちといった、仲間外れを恐れる心理です。
情報的影響
自分より多くの人が同じ選択をしていると「自分が間違っているかもしれない」と感じたりする心理です。
特に不確実な状況下では、自分の判断よりも他人の判断に頼ってしまうことがあり、これも情報的影響によるものです。
安心を得たい心理
周囲と同じ行動、言動をとることで「安全」「間違っていない」と感じることができ、周囲に合わせることはストレスを減らす自己防衛としての役割もあります。
生存戦略
人ははるか昔から集団で生活を営んできた生物です。
そのため、集団から外れることは自分の身が危険にさらされる可能性が高くなることを意味し、周囲に合わせることで生き残りやすい傾向がありました。
なぜ人は「謎基準」に従ってしまうのか
人が「謎基準(同調圧力)」に屈してしまうのは、単なる弱さが原因ではありません。
仲間外れを避けたい(規範的影響)、正しさを求める(情報的影響)、安心を得たい、生存本能といったそれぞれの理由や心理が複雑に絡み合っていることが原因です。
つまり「同調圧力」とは人が社会の中で生き延びるための自然な戦略といえます。
まとめ
この記事では、身近な「謎基準」について様々な理由や心理を紹介しました。
誰が決めたのか、誰が言いだしたのかもわからない、いつの間にか決まっている謎基準。
「なぜ、こうしないといけないのか」と疑問に思う人もいるかもしれませんが、それは人が周囲から仲間外れにならないための生存戦略です。
空気を読むことはとても大切なことで、それができる人はとても協調性が高いと言われることが多いかもしれませんが、人と同じことばかり、空気を読むことばかりをしていては精神的にも良くないうえに、人よりも前に出ることはできません。
あなたが周囲よりも出来る大人になりたい、人よりも有名になりたいと考えるのであれば、同調圧力に屈しない精神力が必要になるでしょう。







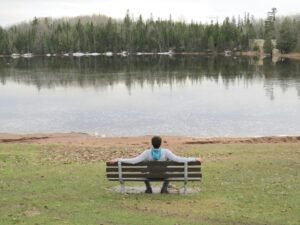


コメント